ためしに意識のあるふりをしてみなさい
「言葉にならないものを表現する」あるいは逆(?)に「目に見えないものを表現する」とは、ごくごく一般的に使われている(半ば陳腐な)修辞なわけだが、これを厳密に達成しようとするなら、それでも様々な困難を伴う。
たとえば、今僕が感じている胃の疼き。それが昨晩から何も食べていないせいなのか、近頃のジャンクフードの食べすぎで荒れているせいなのか、そんな諸々の原因のことは除外しておこう。あるいはまた、であるならば、そろそろ栄養のあるものを摂るべきだとか、胃薬を飲むべきだとかの、何らかの欠如に対する充足案についても、これを保留しよう。つまり、「何か食べたい」とか「痛みを鎮めたい」とかの欲求ないし願望を表わすのではなく、ただ単純にこの状態を表わそうとした場合。たとえばそうした場合の、そもそも距離をとって客体化できないような感覚は、いかにすれば外面的な形象に置き換えることができるのか。そして、それが置き換えられたとして、そのつながりが的確であることを(あるいは的確か否かを判断する基準を)、どのようにして知ることができるのか。
話はおそらく変わって、とある哲学者は次のように書く。
しかし、我々が忘れてはならない一事がある。すなわち、「私が自分の腕を上げる」とき、私の腕は上がるのである。そこで問題が生ずる。私が自分の腕を上げるという事実から、私の腕が上がるという事実を引き去るとき、あとに残るのは何か、という問題である。(ウィトゲンシュタイン『哲学探究』より)
「私が腕を上げる」と「私の腕が上がる」。その差は単に文法上の違いで、言葉の使い方の問題にすぎないようにも思える。ある人は、これは主観と客観、能動と受動という様相的な差であって、それが指し示している事実については、なんら実質的な違いはないのだ、と言うかもしれない。けれど驚くべきことはむしろ、私たちがこの違いを文法上の違いとしてしか表現しえないこと、あるいは言葉の使用を通じてのみ、かろうじて察知しうることであるという点にある。
ためしに「私が腕を上げる」と口にしながら自分の腕を上げ、次に「私の腕が上がる」と言いながら同様の動作をしてみる。何か妙な感じがする。それが何なのかはわからないが、ともかく、ある効果、一定のエフェクトをその時感じる(※間をおかずに何回も反復しすぎると効果がなくなるので注意)。正確に言えば多分それはいわゆる「感覚」ではないのだろう。しかしまるで「感覚することを感覚している」ような、それこそを僕は「感覚」と呼びたくなる。
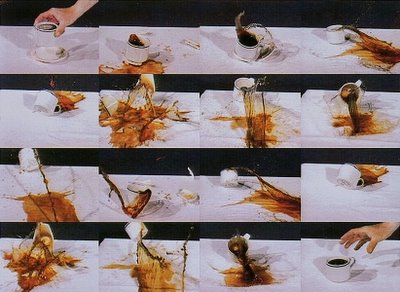
Labels: essay

0 Comments:
Post a Comment
Subscribe to Post Comments [Atom]
<< Home